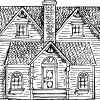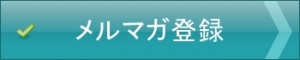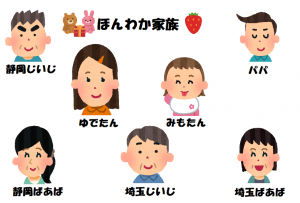相続対策は節税対策だけではない!円満相続のすすめ!
相続対策というと「節税対策」という言葉が思い浮かぶのではないでしょうか?
多くの人がお金がかかる相続税に目が行きがちですが、
相続はそれだけではありません。
正しい認識で相続対策を行っていきましょう!
そもそも相続対策=節税対策と勘違いしていませんか?

「相続対策セミナー」と題して多くの企業がセミナーを行っています。
ハウスメーカー・不動産屋・会計事務所・銀行・コンサルティング会社等、様々な企業が行っています。
しかし、どれも「節税対策」に焦点が当たっています。
もちろん、相続税が安くなることに越したことはないのですが、
「相続対策=節税対策」という認識が広まっていることに非常に危機感を感じています。
本来、相続対策とは、亡くなった際に残された方々が困らずに安心して暮らしていける環境を整えてあげる対策なのです。
もちろんその中には余分な税金を払わないで済むような「節税対策」も含みますが、
それは相続対策の一部にすぎません。
家族で争いが起きないように資産を整理し、納税資金が不足しないように対策をうって
そのうえで節税対策を行うことが本当の相続対策です。
正しい認識で取り組まないと家族が離散するような大変な事態にもなりかねません。
何をすべきかを整理していきましょう。
相続対策の正しい手順

「相続対策って聞くと税金をどれだけ安くするか?」という対策だと思っていましたが、
違うってことですね…
山中さん、その通りです!今は多くの書籍やセミナーで「相続対策=節税対策」と大々的に取り上げてしまっており、このような認識が広まってしまったと感じています。
一度正しい取り組み方について考えてみましょう!
相続対策の正しい手順を考えいきたいと思います。
先ほどお話をした通り、相続対策は
「家族で争いが起きないように資産を整理し、納税資金が不足しないように対策をうって
そのうえで節税対策を行うこと」です。
正しい順序は「争族対策」⇒「納税資金対策」⇒「節税対策」となります。
一番初めに行うことは「争族対策」ですが、その中でも最も大切なのが、資産を持っているご自身が「どんな相続にしたいのか?」という望みを整理することです。
相続とは自分が亡くなった後も家族が幸せに暮らしていけるように意思を示せる場でもあります。
「私が死んでも妻が安心して暮らしていけるだけの資産と自宅を手元に残してあげたい」
「先祖代々引き継いできた土地を守ってもらいながら、家族みんなで仲良く暮らしていってほしい」
「会社の株式は長男に引き継ぎ、経営を守ってもらいたい。長女のためには、自宅を残したい」
など自身の思いまず整理していきます。
実は多くの方がこの手順を間違えてしまい、「争族対策」「納税資金対策」を飛ばして、「節税対策」だけを行ってしまうのです。このような場合は、 相続の際にトラブルを抱えてしまっています。
他の人の失敗のケースから学べ!

よく相談をいただくケースでお話を聞くことが多いのは、
無料で開催されていると聞いた「相続対策セミナー」に参加から始まることが多いです。
すると、そのセミナーはハウスメーカー主催で税理士の方を講師として招いているセミナーのようで、
講師の税理士先生が「そのまま相続が発生するととんでもない相続税がかかります。
借入を行い、持っている土地にアパートを建て、評価額を下げましょう!
「節税対策を進めていきましょう!」と話をしているのを聞いていると対策を打っていない自分に焦りを感じます。
「具体的な話はのちほど相談会で伺います」とハウスメーカーの営業マンを話をすると空地に新築アパートを建てる計画を提案されます。建築をしたタイミングで評価額がさがることは事実なので、その説明に納得して借り入れをして、新築アパートを建ててしまうのです。
もちろん、アパート運営がうまくいっていたり、自身が望む相続の形に近づけるための戦略にアパート建築をとりいれることはもちろんありますが、本来であれば、「その土地は子孫に残したい土地なのか?」「誰に引き継がせたいのか?」「引き継がせるためには最適な手段はなのか?」などその前に検討すべきことがあるはずなのに、「節税対策」が先走ってしまっていることが問題なのです。
ほとんどのケースで「相続対策=節税対策」と認識してしまっていることが原因でこのような失敗は起こります。
知り合いの会社の社長もアパート立てると言って、持っている土地にどんどんアパート建ててたな。ちょっと心配になってきた。
相続対策はいつから行うべきか?

相続対策はどれくらいから考えればいいのでしょうか?
対策を取られていない方は、今からです!
というのも、相続の対策には非常に時間がかかります。
数か月で準備が整うわけではなく、数年単位で対策を行うのが相続対策です。
納税資金が不足しないように資産を管理し、そのうえで節税対策を行う。そして、次世代のことを考え分けやすい資産にしていくことが必要です。もちろん、すべての資産が現金であれば、対策も短期間で済みますが、多くの資産家の方は不動産で資産をお持ちの方が多いため、納税に使える現金が不足していたり、先祖代々の土地であり、複雑な権利関係の土地をお持ちであったりと対策には時間を要することが多いです。
相続の相談は誰にすればいいの?

そもそも相続の相談は誰にすべきなのでしょうか?
相続相談を行っている会社は様々あります。
ハウスメーカー・不動産屋・葬儀屋・コンサルティング会社・税理士・弁護士・ファイナンシャルランナーなど誰に相談すべきなのか、迷ってしまいます。
私個人的にはどのような方に相談するとしてもまず「相続専門」でやられている方に相談することをおすすめしています。
なぜ「相続専門」でやっているということなのかというと
顧問税理士がいらっしゃる方で相続の相談をそのまま先生にお願いをしているというケースをよく伺います。
考えを整理するために会計事務所を例に挙げ、考えてみましょう。
会計事務所の税理士先生は税務のプロです。もちろん相続税申告はできます。しかし、会計事務所は申告の種類によって得意不得意があるのです。
税理士試験は、5科目合格が条件であり、実は相続税を受験せずに税理士資格を有している方も多くいらっしゃいます。また事務所によっては、相続専門事務所を経営されている先生であれば、年間100件ほどの相続税申告に関わっていることもあれば、法人税申告を専門としているため、相続税申告は年に1件あるかないかという先生もいらっしゃいます。
このようなことは他の業種でもいえることで、弁護士でも離婚訴訟が得意な先生がいたり、それぞれの得意分野を持っているため、必ず相続を得意としている「相続専門」の方への相談が必要です。
まとめ

「相続対策=節税対策」という認識をなくし、
「争族対策」「納税資金対策」「節税対策」 の3つの対策をじっくりと練り上げ、実行していくことが相続での失敗をなくすポイントです。
まだまだ先とお考えの方も相続対策には時間を要します。
気になったタイミングから動き出すことが必要です。
是非一度、検討してみていただければと思います。